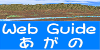白鳥の湖 瓢湖(ひょうこ)
<地図はこちら> |
 |
Webを検索 www.agano.net を検索 |
| <<瓢湖に関する過去の記事>> |
○瓢湖の白鳥と野鳥達(2005.10.26) ○瓢湖の野鳥達(2005.12.16) ○白鳥の旅立ち(2006.03.15)
○瓢湖などの桜(2006.04.19) ○瓢湖に白鳥がやって来ました(2006.10.14)
○瓢湖の花火大会(2006.08.25) ○瓢湖で灯篭流しが開催されました(2007.07.17) |

(平成17年12月16日撮影、後は五頭連峰)

(平成17年10月26日撮影)

(平成18年3月15日撮影、遠方の山は二王子岳) |
新潟県阿賀野市で最も有名な観光地である白鳥の湖「瓢湖(ひょうこ)」は、阿賀野市のホームページによれば、江戸時代の寛永2年、この地帯が大干ばつにあい、その解決策として翌年(1626年)に当時の領主、新発田藩主が工事を起し、寛永16年(1639年)に13年の歳月を要して完成したそうです。
昭和29年(1954)2月5日に吉川重三郎氏が白鳥の餌付けに成功し、同年2月には県、同3月には国の天然記念物に指定。
白鳥は、例年10月初旬に渡来し、3月初旬にはシベリアなどの北極圏に向けて旅立ちます。コハクチョウはオオハクチョウより北のツンドラ地帯で繁殖するそうです。
瓢湖では、給餌が9:00 11:00 15:00の三回行われていますが、田んぼに積雪がない限り殆どの白鳥たちは近隣の田圃(たんぼ)へ粃(しいな=実が入っていない米の籾殻)を食べに出掛けています。従って、左の写真のような状況では、瓢湖にはわずかな白鳥しか残っていません。
近隣の田圃では、オオヒシクイの群れが白鳥の群れと一緒にいることも多々ありますが、オオヒシクイは警戒心が強くてなかなか近づけません。 |

(平成19年4月15日撮影)

(平成18年4月19日撮影)
|
例年、4月も半ばを過ぎると阿賀野市各地の桜も満開を迎えます。
怪我でもしたのか、体調が悪いのか。それとも留鳥を決め込んだのか。
居残り組の白鳥やカモ類と五頭連峰の残雪、それと満開のソメイヨシノ。
冬と春が同居しています。 |

(平成18年6月14日撮影)

(平成18年6月14日撮影) |
瓢湖に隣接する「あやめ園」で、6月上旬から下旬にかけて「あやめまつり」が開催されます。
上の写真は、ハナショウブでしょうか?
”アヤメ”も”ハナショウブ”も”カキツバタ”も単子葉植物の”ユリ目””アヤメ科”に分類されます。
ちなみに、”ショウブ”は、”サトイモ目”に分類されます。
|

(平成19年7月16日撮影)

(平成19年7月15日撮影)
 |
平成19年7月16日、白鳥の湖瓢湖で灯篭流しが行われました。
この時は、せっかくの幽玄な雰囲気を三味線が吹き飛ばしていました。
真ん中の写真は、灯篭流しの前日に瓢湖で撮影したライトアップされた噴水です。
噴水のライトアップは、週末だけでしょうか?前年は、7月25日の花火大会の開始直前までライトアップが行われていました。
下の写真は平成18年8月25日に撮影した水原まつりのフィナーレ「瓢湖の花火大会」の一尺玉です。
例年、新潟市の松浜祭りの花火大会も瓢湖の花火大会と同じ日に行われます。
遠くに見える松浜の花火の打ち上げ間隔は大変短いため、瓢湖の花火の間隔がとても長く感じます。
しかし、瓢湖の花火の場合は、見物客も少ないため打ち上げ場所に近寄って見るスターマインと一尺玉にはなかなか感動します。
(ちょっと瓢湖に味方しました)
|


|
この白鳥は、オオハクチョウの番(つがい)でしょうか。
コハクチョウとの見分け方は、嘴(くちばし)の黄色い部分が大きい方がオオハクチョウです。
オオハクチョウの幼鳥の嘴は灰色です。 |

(平成21年1月25日、阿賀野市笹神地区で撮影)
クリックするとコハクチョウの音声動画が表示されます

瓢湖のコハクチョウ

(平成19年11月8日、阿賀野市笹神地区で撮影) |
この白鳥は、コハクチョウ。
上の写真は、氷結した冬水田んぼのコハクチョウ。写真をクリックするとコハクチョウの鳴き声と動画が表示されます。
オオハクチョウと比較すると、嘴の黄色い部分が小さく、体も一回り小型です。
真ん中の写真は瓢湖のコハクチョウ。
下の写真は、阿賀野市笹神(ささかみ)地区で撮影したコハクチョウ。 |


 |
平成23年12月14日
阿賀野市熊堂地区の田んぼにマガンとオオヒシクイがやって来ていました。
福島潟から直線距離で3km程度はなれた田んぼで白鳥とオオヒシクイ、マガンが食餌。
(上の写真)
嘴黄色いはオオヒシクイ。
額が白いマガンより随分大きな冬鳥です。
(真ん中の写真)
額が白いマガン
(下の写真)
嘴が黄色いオオヒシクイ
|

(平成19年11月8日、阿賀野市笹神地区で撮影) |
左の写真は、オオヒシクイ。白鳥と同じカモ科の水鳥で、ガンの仲間です。
瓢湖から直線距離で10km程度はなれた福島潟で越冬しており、白鳥と同じように、積雪のない時期は田圃でエサをついばんでいます。
(瓢湖では見たことがありません。)
餌付けされていないためか白鳥より警戒心が強くて、なかなか人を寄せ付けてくれません。 |


(平成19年1月21日撮影)
|
左の写真は、オナガガモのオス。
この日は、午前7時27分に太陽が五頭連峰から顔を出しました。
撮影したのは、約1時間後の8時33分。
放射冷却で晴れ渡ったため、気温は氷点下。
それでも、強い直射日光が眠気を誘うのか、まぶたが重くてなかなか目が開きません。
|

|
左はクイナ科のオオバン。
白い額板があるため他のガンカモ科の水鳥たちと容易に区別がつきます。嘴が白いことも特徴的で黒っぽい体と対照的です。
沖縄本島に生息するヤンバルクイナと同じく、これでも鶴の仲間です。 |
 |
ヒドリガモのメス。”緋鳥鴨”と書くそうです。
瓢湖では、オナガガモと同じく大変数の多いカモです。
|
 |
キンクロハジロのオス。
黄色い色に黒い色の羽が特徴です。
”金黒羽白”と書くそうです。
瓢湖では、比較的数が少ないカモです。
|
 |
マガモ
アヒルの先祖と言われています。
瓢湖では、比較的、数の少ないカモです。 |
 |
中央の頭が緑色で嘴が黒いカモがハシビロガモ(嘴広鴨合鴨)のオス。 くちばしが幅広い事が特徴。
瓢湖では珍しいカモです。
|
| 以下平成21年12月24日撮影 |
 |
○オナガガモのオス |
 |
○キンクロハジロのメス
焦げ茶色で小さい"寝癖"が特徴 |
 |
○ヒドリガモのオス |
 |
○オオハクチョウの幼鳥
成長になると嘴(くちばし)の白い部分が黄色くなります。 |
 |
○ホシハジロのオス
赤い目(光彩)が特徴 |
 |
○瓢湖での給餌
給餌は、9:00 11:00 15:00の三回
行われ、カモ類が殆ど食い尽くします。
周囲の田んぼでは積雪が10cm余りあってエサを食べられないので、普段は余りいない白鳥も今日は結構一杯いました。 |
 |
○トビ
瓢湖の桜並木にたむろしていますが、群れで警戒し合っているカモ類を狙ってもなかなか獲物にありつけません。 |
 |
○カワウ
近頃、瓢湖で良く目にします。
|
| WebGuide阿賀野 |
白鳥の湖 瓢湖 |
|
|